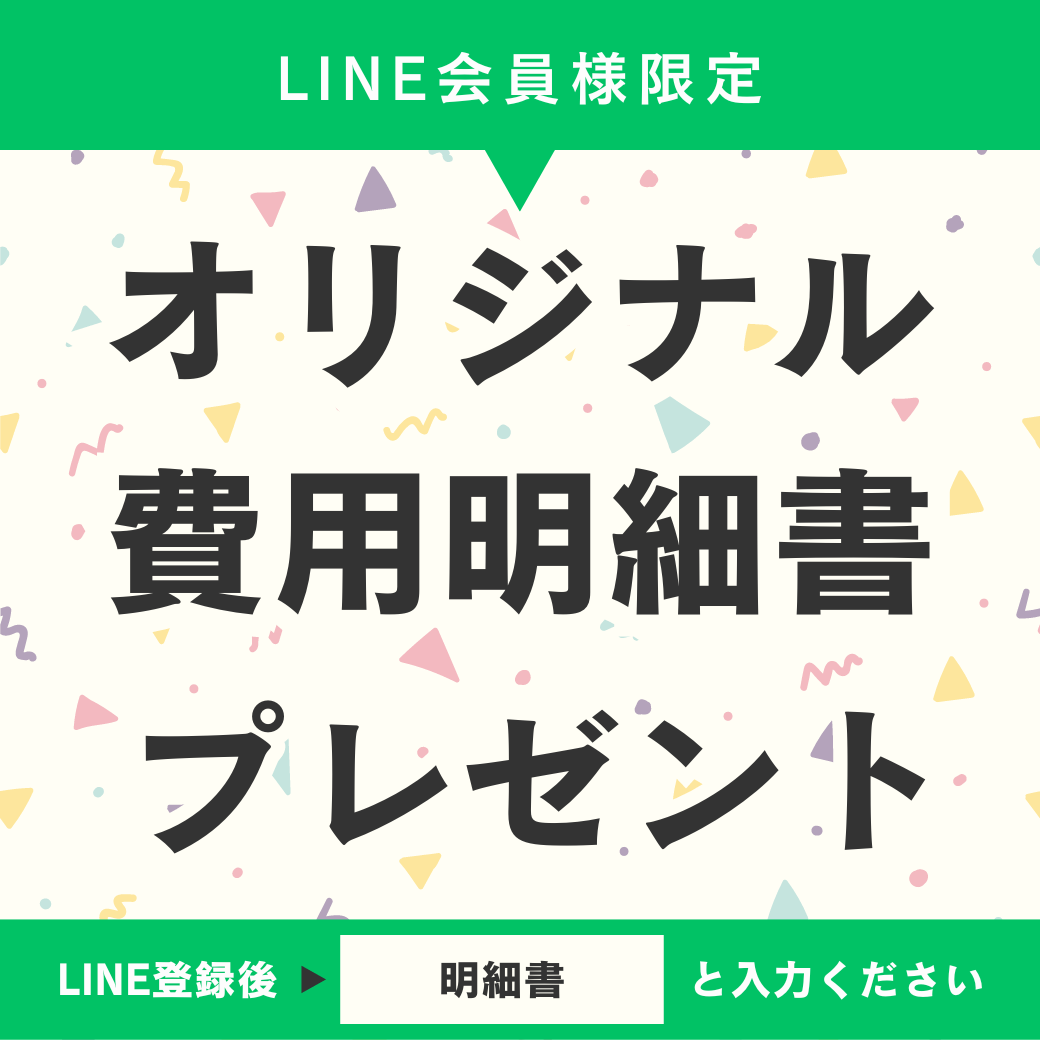- 不動産業者として開業を考えている
- どんな流れで進めていくか勉強したい
- 開業のアドバイスをもらいたい
- 何から始めて良いか分からない
上記の悩みや、これに近い疑問を持っているなら必ず御覧ください。
不動産業者として営業するには最短でも2ヶ月かかります。
事前準備を怠ると、営業できるまでの期間も延びますし、無駄な費用がかかってきます。
効率よく開業するには、あなた自身で知識を付けて行動していくしかありません。
営業開始というゴールまでは様々な手続きや申請という障壁がありますが、本サイトを上手に利用してください。
無事に不動産de開業出来ることを心より願っております。
事前準備
不動産業を開始するには、開業前からの動きが重要になってきます。
事前準備をしっかりと行うことで開業まで最短で行くことが可能です。
一番面倒だと感じる部分かもしれませんが、時間的に余裕がある初段階で固めておきましょう。
自己資金を貯める
まずは自己資金を貯めることです。
何故なら、不動産業を開始するだけで200万円近くの費用が発生するからです。
また、不動産業を開始してすぐに入金されるわけではないので、数カ月分のランニングコストも必要になります。
大前提として自己資金はきっちりと貯めておきましょう。
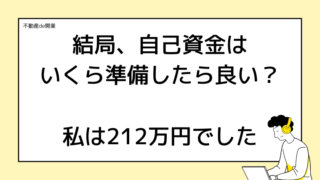
ただ、自己資金になるお金とならないお金があるので違いを知らないと失敗します。
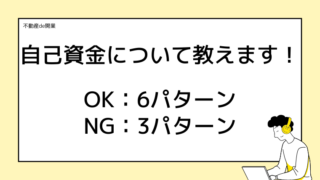
不動産業を経験しておく
よくある質問として、未経験でも開業出来ますか?というのがあります。
結論から伝えると、独立前に不動産業は経験しておいた方が良いです。
1つ目の観点は、開業できるけどある必須条件が大事になってくる点です。
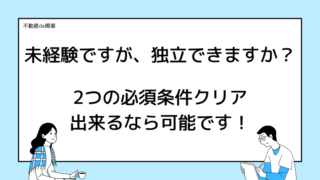
2つ目の観点は、未経験だとぶち当たる3つの壁があるからです。
こちらは営業スタートしてから特に大事になってくる要素を解説しているので、絶対に見ておくべき内容です。
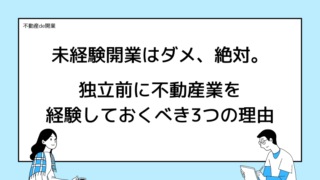
仕事内容を決める
次は仕事内容(業務形態)についてです。
- 賃貸仲介専門
- 売買仲介専門
- 管理専門
- 投資用マンション専門
- 買取専門
など、不動産業者と言っても様々な仕事があります。
1人で開業となると、ある程度仕事内容を絞らないと上手に軌道に乗せるのが難しくなります。
そういった観点からも、事前に不動産業の経験はしておいたほうが良いとなります。
法人か個人か決める
次は、法人か個人か決めましょう。
不動産業者といっても法人化している所もあれば、個人事業主として運営している所もあります。
開業前に法人か個人か決めておかないと、次のステップへ進めなくなるので必ず決めておきましょう。
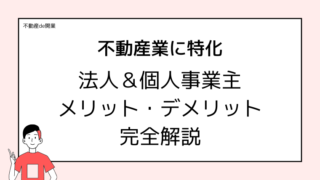
ちなみに私は、株式会社おもいで不動産という法人で開業しました。
宅建士の確保
あなたが代表者かつ宅建士の資格を保有しているのであれば問題ありません。
ただ、保有していない場合は宅建士は必ず必要になるので、確保しておく必要があります。
また、宅地建物取引業の免許申請の段階で専任登録が必要になるため、雇わないといけません。
営業が出来ない中、数ヶ月間人を雇うのは非常に大変なので、代表者自身が宅建士の資格を保有しておきましょう。
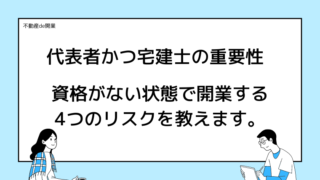
勤務会社に退職の連絡を入れる
宅地建物取引業は常勤性を求められるので、副業として開業は出来ません。
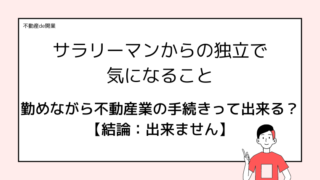
そのため、開業に動く前に現在の勤務会社へ退職する旨を伝えましょう。
不動産業者に勤めているかつ専任登録をしている場合は、解除してもらわないといけないので注意しておきましょう。
ただ実は、会社での手続きは会社がしてくれますが個人での変更手続きもあります。
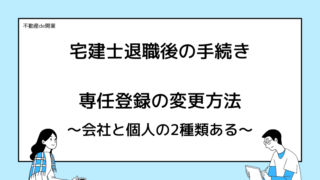
〜宅地建物取引業免許の申請まで
事前準備が一段落ついた頃から、次のステップも進めていきます。
このあたりから実質無職かつ、お金の出費が発生してくるので、必ず自己資金を持った上で行動していきましょう。
会社名の考案
まずは会社名の考案です。
法人・個人問わずに会社名という看板を背負いますのでネーミングが大事になってきます。
- 株式会社おもいで不動産(当社)
- 不動産の〇〇
- 〇〇エステート
- 野上不動産(自分の名字)
- 〇〇ハウス
- 〇〇ハウジング
会社名は一度決めると、経営している限りずっと名乗り続けるので、勢いだけで決めるのは絶対にやめましょう。
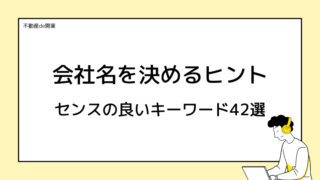
またルールもありますし、不動産業者としての会社名の考え方もあるので、まずは知識として勉強してから候補を出すことを強くオススメします。
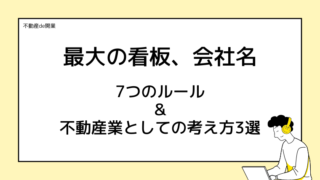
印鑑の作成
会社名が確定すると、次は印鑑の作成を行います。
最初の段階では、会社印があれば問題ありませんが、今後の事を考えると以下の3本を準備しましょう。
- 会社印(丸印)
- 会社印(角印)
- 銀行印
おすすめの印鑑作成
事務所を借りる
不動産業は申請のタイミングで事務所がないといけないので、最初に借りておかないといけません。
ただ、ここで大事になってくるのが以下の3つです。
- どのタイミングで借りるのか
- 個人・法人どちらで借りるのか
- 事務所の要件(定義)
私の場合、退職前に個人で事務所を借りて、その後、法人へ使用貸借契約で貸し出す方法を取りました。
理由は全部で2つです。
- 法人登記まで待つと埋まる可能性があったため
- 個人の信用がある段階で借りた方が良いと判断したため
事務所を借りるタイミングによって、決めて行くのが良いでしょう。
会社設立
事務所を借りることが出来たら、会社設立を進めていきます。
個人事業主で行う場合は法人登記は不要なので、次へ進めて大丈夫です。
会社設立について
固定電話番号の取得
会社設立と同じタイミングで必ず固定電話番号の取得をしておきましょう。
何故なら、宅地建物取引業では固定電話が必須だからです。
また、不動産業はFAXで書類のやり取りを行うことが多いので、同時にFAX番号も取得しておくことをオススメします。
オススメの電話会社
宅地建物取引業免許の申請書類の取得
不動産開業をするには、宅地建物取引業免許の申請をしないといけません。
そして、提出先は2ヶ所あります。
- 土木事務所
- 宅建協会
それぞれにおいて、提出すべき申請書類があるので取得しましょう。
宅建協会で土木事務所及び宅建協会の両書類を取得できます。
申請書の書き方について
必要書類の取得
宅建業の書類には記入するものと取得するものがあります。
ただ「法人か個人か」よって必要書類が変わってくるので注意が必要です。
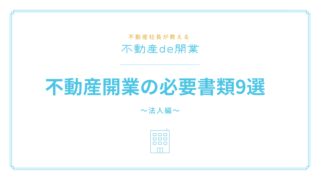
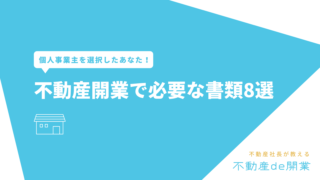
私自身、最終的に必要な枚数を知らなかったために何度も市役所や法務局へ行くことになりました。
段取りは本当に大事なので知っておきましょう。

また、私も勘違いしていた身分証明書と登記されていないことの証明書の違いについても理解しておきましょう。
結論から言うと、取得場所も違う別書類なので、両方とも準備しないといけません。
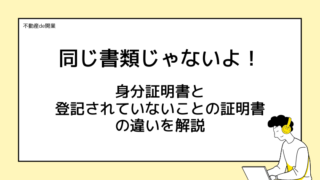
推薦人2名を探す
宅建協会から書類をもらいますが、その中に推薦人2名から開業に関する押印をもらわないといけません。
また、推薦人になるための要件が2つあります。
- 開業5年以上
- 自由民主党福岡県宅建支部の会費を延滞していない
また、2名のうち1名は自分の開業エリアと同支部じゃないといけません。
基本的に代表者の知人友人になってもらうことが多いですが、未経験の場合は知り合いがいないこともあります。
どうしても見つからない場合は宅建協会に相談すれば対応してくれますが、やはり自分の周りから探すのがベストです。
そういった観点からも事前に不動産業を経験しておくことをおすすめします。
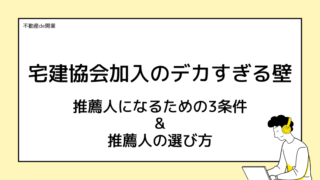
地区部長の承認をもらう
2名の推薦人の押印が終わったら、開業エリアの地区部長へ連絡をしましょう。
※連絡先は宅建協会の申請時に教えてもらえます
日時を調整して、地区部長の事務所へ伺い書類に押印してもらいます。
私の場合、優しいお言葉をもらえてスムーズに承認いただけたので、時間にして15分程度で完了しました。
宅地建物取引業免許の申請
色々と動きましたが、以下の段取りが完了したら、宅地建物取引業免許の申請に行きましょう。
- 申請書類の記入
- 必要書類の準備
- 推薦人2名&地区部長の押印
ただ、宅建協会は土木事務所の受付印が入った申請書類が必要なので以下の流れで進めていきましょう。
- 土木事務所
- 宅建協会
土木事務所の流れ
宅建協会の受付流れ
土木事務所受付のタイミングで33,000円が必要になるので準備しておきましょう。
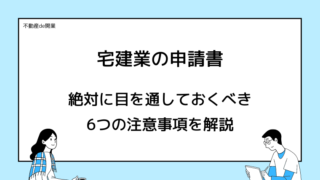
宅建協会の書類の中に、口座引落の書類が入っていますが、法人の場合は口座作成が出来ていないことが多いです。
事前に連絡を入れておけば、口座開設できた後の申請でも大丈夫なので落ち着いてから口座作成しましょう。
〜免許許可が下りるまで
宅地建物取引業免許の受付から免許が下りるまでの間にやるべきことがたくさん出てきます。
受付から免許が下りるまでの流れ(全体像)
この間の行動次第で、開業までの期間が変わってくるので段取りよく進めていきましょう。
見積書を集める
開業の際、事業資金の借入を行うと思いますが、借りるための根拠が必要になります。
次に出てくる事業融資では、創業計画書を書きますが、必ず見積書や金額が掲載されている資料が必要になります。
私が揃えた見積書関係:合計352万円
- 150万円:車購入の見積書
- 166万円:宅建協会加入金
- 17万円:パソコン
- 14万円:電話(ネットFAX)
- 5万円:プリンター
※ホームページは自作出来たので最終的には創業計画書に入れませんでしたが、当初は60万円の見積書を用意しました
実際に利用しているツール一覧
実際に見積書をもらうまでには以下の段取りをしないといけないので、宅地建物取引業免許の申請前から動き出しても良いです。
見積書をもらうまでの段取り:約1週間〜2週間かかる
- 自分にあった商品やツールを探す(ここが一番重要)
- 問い合わせをする
- 打合わせの日程調整
- 打合わせて自分の希望を提案&話を聞く
- 見積書をもらう
開業の相談をする
事業融資(日本金融政策公庫)の書類作成
見積書を集めている、もしくは完了した段階から事業融資の書類作成を進めていきましょう。
私は日本金融政策公庫で借入申請をしたので、そこを前提としていきますが記入すべき書類があります。
- 借入申込書
- 創業計画書
- 月別収支計画書
- 追加資料
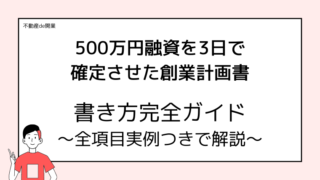
基本的には借入申込書と創業計画書があれば良いですが、既存の資料だけだと薄い内容した伝えられません。
そのため、月別収支計画書で1年間の流れを説明して、追加資料で自分の魅力を伝えていきましょう。
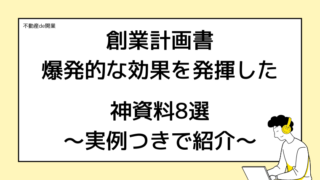
資料が揃った段階で日本金融政策公庫へ資料を郵送で送付します。
口座開設
口座開設をしようと思っても、現在はかなり厳しくなっているので1日で作成は出来ません。
約2−3週間かかる事が多いので、ゴールを見据えた上で行動していくことが大事です。
私が創業前に開設した口座
- 福岡銀行:約10日間
- 福岡しんきん:約20日間
口座開設に必要な書類
事務所のインフラ整備
申請前に申込した固定電話番号ですが、業者が忙しいことが多いので、基本的に開通工事まで1ヶ月間ほどかかります。
私の場合、固定電話の開通工事のタイミングでwi-fiの設置などを行いました。
土木事務所の事務所調査までには固定電話がつながるようにしないといけないので、段取りしておきましょう。
宅建協会の面談
宅地建物取引業の申請から約20日後あたりで宅建協会の面談があります。
日時は申請のタイミングで教えてくれますが、面談には以下の人間が必要になるのでそれぞれのスケジュールを合わせないといけません。
- 会社の代表者
- 専任の取引士
- 同じ支部の推薦人
面談時間は約15分で完了しますが、事前に準備しておくものや当日の流れを知っておくことは大事なので必ず見てください。
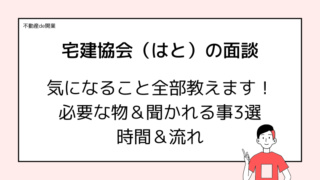
日本金融政策公庫の面談
日本金融政策公庫へ資料を送付して1週間以内程度で面談日の調整連絡が入ります。
事前に創業計画書などを送付していますが、面談当日には通帳や賃貸借契約書など用意すべきものが沢山あります。
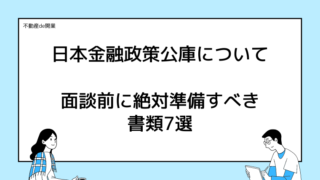
また、必ず聞かれる項目や説明すべき項目があるので事前準備が本当に大事になってきます。
ここを怠ると、借入金額が減ったり・借入自体が非承認になることもあるので注意しておきましょう。
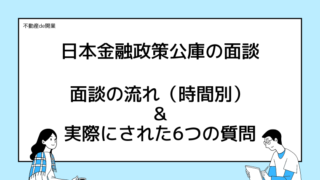
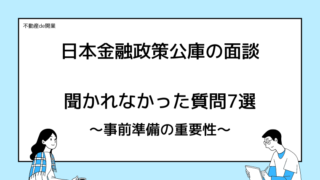
面談完了から事業融資までの流れ
土木事務所の事務所調査
宅地建物取引業の申請から38日後に土木整備事務所による事務所調査が行われました。
事前に準備すべきものもありますし、当日確認されるポイントも6つあるので、事前に勉強して事務所調査に臨みましょう。
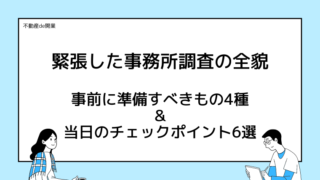
入会資格者研修の受講
本来であれば、宅建協会へ申込みしてから1ヶ月後程のタイミングで、入会資格社研修が行われます。
福岡市の場合、東区馬出の本部で受講しますが、私の場合コロナの影響で中止になりました。
そのため、郵送で書類が送られてきて試験(10問)を行って返送することで受講したことになったので楽でした。
本来であれば、13時から17時位までの時間を使って行うので、忘れないように予定を入れておきましょう。
日本金融政策公庫との契約
私の場合、融資面談の際、先に宅建協会へ加盟金167万円を支払わないといけないので、免許が下りる前に融資して欲しいと相談しました。
その甲斐あって、宅建業の許可が下りる前に融資実行してもらうことができました。
融資が確定したら、日本金融政策公庫から契約書類が送られてくるので、必要なものを揃えて返送しないといけません。
特に事前に銀行口座を作っておかないと悲惨なことになるので、必ず事前に内容を確認して段取りしておきましょう。
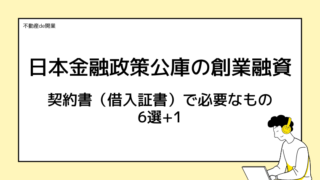
免許番号確定
土木事務所の調査が終わった後に、土木整備事務所から宅地建物取引業の承認が下りたことの連絡が入ります。
この段階で宅建業の免許番号が確定しますが、私はそのタイミングで番号を聞き忘れました。
私の場合、事務所調査の翌日に連絡が入ったので、意外と早かった印象が残っています。
決定通知書の受取り
連絡があって10日後くらいに決定通知書のハガキが事務所に届きます。
やっとここまで来て、不動産業者になったという嬉しさが出てきます。
ただ、まだ供託金等を支払っていないので宅地建物取引業者として活動することが出来ませんので注意してください。
〜開業まで
宅建番号が決まってからは、様々なことが動き出すのでとても大変です。
更にスピーディに手続きをしていかないといけないので、忙しくなります。
ホームページ作成
まずは、ホームページ作成の着手をしないといけません。
ホームページは基本的に依頼をしてからオープンまで1ヶ月間ほどかかるので、事前に段取りしていても問題ありません。
私の場合、万が一免許が下りなかったときのことを考えて免許番号が確定してから動き出しました。
供託金の支払い
このタイミングあたりで以前、日本政策金融公庫との契約を行っていた手続きが完了しています。
いわゆる借入金の振込が完了しているということです。
そのお金を使用して供託金の支払いを行いましょう。
供託金の他に支払いをしないといけないので、すべて完了させましょう。
分担納付書交付
供託金の振込が完了した次の木曜日が宅建協会の供託日になります。
そのタイミングで、宅建協会から連絡があるので、宅建協会本部へ行きましょう。
そこで領収書の受け取りや分担金納付書が交付されます。
この分担金納付書が無いと、土木事務所での手続きが出来ないので注意しましょう。
分担金納付書(写)を土木事務所へ提出
宅建協会から分担金納付書を受け取ったら、以前受け取った決定通知書(ハガキ)と合わせて土木事務所へ行きましょう。
分担金納付書を土木事務所へ提出することで、すべての手続きが完了となります。
営業許可証の交付
土木事務所で手続きが完了すると、最後に営業許可証が交付されます。
ここで始めて不動産業としてスタート出来ると思いますが、不動産業というのは2つの手続きを完了しないといけません。
- 供託金の支払い
- 土木事務所での手続き
上記2つの手続きを完了させた次の木曜日が供託完了日となるため、ここから営業開始することが出来ます。
最終的には宅建協会に確認することをオススメします。
不動産業者としてスタート
ということで、ここまで来て始めて不動産業者としてスタートさせることが出来ます。
非常に長い道のりでしたが、不動産業者として仕事をするために、必ず通らないといけません。
開業してからのほうが大変ですが、頑張っていきましょう。
本サイトを通じて、少しでも不動産開業手続きの手助けになっていれば幸いです。